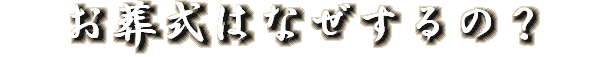
|
||||
|
Q: そもそも葬式をやらないという家庭も増えそうです。 「何も特別なことする必要なんてないじゃないの」と一昔前の日本人なら聞いて腰を抜かしかねない考えも、ちらほら、少しずつ、そんなに珍しくなく、出てくるようになりました。 「お葬式」を「社会的な儀礼」もしくは「イベント」と考えるから、「お葬式なんていらない」という考えが出てくるわけです。 1960年代の高度経済成長期以降バブル景気が終焉するまでのお葬式がちょっと方向を間違えたことが影響しています。あの時代が異常だったのです。 お葬式の原点は「人の死」です。それも「知らない人の死」ではなく「親しい人、近親者の死」です。 60年代から90年代の始めまでの時期はここを間違えました。何せお葬式の会葬者の7割が「亡くなった本人を知らない人」が占めたのですから。つまり「悲しんでいない人が圧倒的多数」というお葬式が幅をきかせたのです。 家族や親友の死が与える影響の大きさは知っているでしょうし、たとえ経験していなくとも想像はできるでしょう。 かつて教えていた学生に「家族の死、配偶者の死、子どもの死、恋人の死、親友の死を想像してみよう」と言ったら、そこにいた多くの学生が「そんな悲しみに出合ったら、私は耐えられないでしょう」と答えました。 そうです。「自分が愛している人の死」は、耐えられない悲しみ、あるいは一時的にその悲しみを封印せざるを得ないような、あるいは一切の感情表現を抑えこまざるを得ないほどの悲しみ(グリーフ)をもたらすのです。 「死者を悼む」と簡単に言いますが、人間が真の底から死者を悼むのは、その故人をよく知っているからです。個人的に表現するならば、悲しみというのは感情だけの話、心や気持ちだけの話ではなく身体も傷むのです。自分をコントロールできなくさせます。 死者のことを個人的によく知らない場合は、一瞬「かわいそうに」と同情はしますが、めったに「死者を悼む」ことができるほど人間は上等にはできていません。また「悼む人」「悲しむ人」は家族とはかぎりません。 Q: 背景に人間関係や家族関係の変化があるのでしょうか。 A: そうだと思います。家族関係が壊れていた場合、その家族は死者に冷淡なものです。そうした「悲しまない家族」が増えているようにも感じます。いろんな意味での「仲間」はときとして「家族以上」に悼み、悲しみます。 お葬式とは「死者を悼み、悲しむ人によって営まれる心的プロセス」に本義があるのではないでしょうか? そうであるならば「お葬式はなぜするのか?」ではなく「愛する人の死に出合った人によるせざるを得ないプロセス」がお葬式なのです。 80歳を超えた人が亡くなることが多くなったこともあるのでしょう。「もう充分にがんばって生きた。もうご苦労さん。ありがとう」というようなお葬式もあるでしょう。 人間が家族を作ったり、仲間を作ったり、関係の中で生きており、そのあり方は多様です。何も「泣くお葬式」ばかりではなく「感謝するお葬式」もあるでしょう。その死者を囲む人間関係がもたらすものです。どれもありでしょう。 お葬式で「死者の尊厳」が大切なのは、その人が世間的に成功した人であるかどうかに関係なく、その「いのち」がかけがいのないものだからです。 どんな人にも尊厳はあります。家族がその尊厳を無視するならば、代わって仲間や宗教者や葬祭従事者がその尊厳を守ろうとするでしょう。そして、そこにも「お葬式」はあるのです。 Q: これだけ葬式に対する価値観が変動すると、自分がどうすればいいのかが分からなくなります。 A: 「お葬式がわからない」という人が増えています。それは「お葬式そのもの」がわからないのではなく、「社会儀礼としての手順」や「約束事」がわからないだけの話のように思えます。そして、皆さんは心配しますが、社会的手順や約束事は知らなくてもお葬式は立派にできます。わからないところは、それこそ「プロ」の宗教者や葬祭業者がサポートしてくれるはずですから、そんな心配は不要です。 「家族葬は呼ばれたら行く、呼ばれなかったら行かない」のでしょうか? その答は自ずから明らかです。死者と自分の関係を考えればいいのです。 恋人の葬式に出られず部屋でその時間一人で悼む、というのもありでしょうし、押しかけて無理だったら出棺だけでも見送る、というのもありでしょう。後日に訪問して弔意を表すのも、手紙を書くのも、皆ありです。 私自身は、お葬式で周囲の親しい人に困惑を与える方式はいいとは思いませんけれど。 |
||||
| TOPページ | ||||