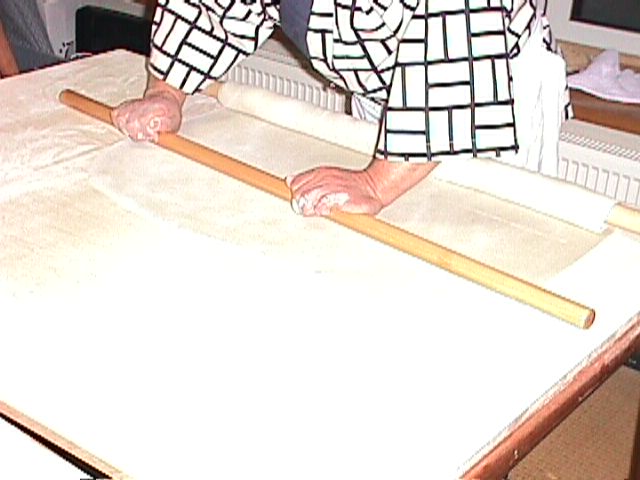NEW ! 蘭越
・黒松内産 |
15.11~蕎麦イベントに使用。好評。抜きを石臼で挽いた粉。水で10割蕎麦が繋がります。この粉が私の蕎麦打ちの
ベースです。価格も安くいい粉ですので…
近年、国道5号線沿いの以前牧草地や水田だったところに蕎麦を栽培しているのを目にします。黒松内町なので黒松内産かも・・・。また、蘭越に入ると減反後の水田に随分と蕎麦の栽培が目立つようになりました。蘭越産は「ふるさとの丘」や町の中心部にある農協の下のコープで販売しています。打ち粉付きです。
|
| NEW ! 幌加内産 |
 15.9~ 「世界そばフェスタ」や蕎麦まつりに参加 15.9~ 「世界そばフェスタ」や蕎麦まつりに参加
そば打ちを始めた頃はもっぱらここの粉を使っていました。コープに注文したり、お土産に戴いたり、幌加内や札幌の蕎麦祭りで買い求めたりで随分打ちました。色が黒っぽい二番粉ばかりでした。コシがある粉です。幌加内は蕎麦生産日本一なので、ここの粉は間違いがないとの思いがありました。
今回、北村製粉の荒挽きの石臼挽き蕎麦粉は素晴らしい粉でした。これからも取り寄せたいと思います。何より主に誠意があります。ここが大事、これがあれば一層蕎麦粉にうまみが増します。私のイチオシしの蕎麦粉です。
|
| NEW ! 新得産 |
 15.11~蕎麦イベントに使いたくてコープから送ってもらいました。田舎蕎麦系です。風味があり、蕎麦好きには大人気でした。送料等プラスアルファーが多いのがマイナス。 15.11~蕎麦イベントに使いたくてコープから送ってもらいました。田舎蕎麦系です。風味があり、蕎麦好きには大人気でした。送料等プラスアルファーが多いのがマイナス。
蕎麦打ちを始めた頃によく打ちました。それは北海道の蕎麦と言ったら「新得」と思っていましたから・・・。お土産で戴いたり、鹿追に行った際、「新得そばの館」でも購入し打ちました。味の割には高価との思いがあるのですが・・・。 |
| NEW ! 清里産 |

15.11~北海道知床の清里産蕎麦粉です。非常に良い粉です。知人の娘さんが地元に在住とのことで頂きます。なかなか手に入らない、貴重な粉です。 |
| 函館亀尾産 |
町おこしの一環として、若者を中心にしてソバの種まき、花見会、収穫祭と函館市民に呼びかけ、話題を呼んでいます。今年(14年)の収穫祭では蕎麦打ちの指導と言うことで依頼があり協力しました。腰があり、余りの歯ごたえに堅いと思うほどでした。 |
| 厚沢部産 |
町に入ってすぐのコープで販売していました。10割りで打ち食べたが,甘みが強く美味しかった。ここでは蕎麦打ち道具も展示販売しています。また,すぐ近くの道の駅でも素掘りの練り鉢を販売しています。 |
| 上士幌産 |
帯広の学校の教師を している教え子が時々送ってくれます。なかなかよい粉です。 |
| 音更産 |
今年(14年)の新蕎麦を戴きました。黒っぽい3番粉の色をしていました。腰がありとても美味しい粉です。 |
|
|
| 鹿追産 |
13.10~ 蕎麦まつりに参加
西上農園のぬきの石臼挽きの蕎麦粉には惚れています。緑の薄皮を残した丸ぬきを石臼で挽いた粉です。打つ際には焦げるような強い香りがするのがたまりません。茹でると緑っぽい色で、喉越しも良く、コシはもちろんあります。余り蕎麦を好まない私にとって、「おいしい」と思う蕎麦粉です。
また、ここの打ち粉は真っ白で一番粉でとても良いものです。この蕎麦粉にはこの打ち粉がぴったりです。
農業振興公社でも送ってくれます。この粉は二番粉です。「ひきぐるみ」もありますが、非常に粘りのある粉で、水だけで10割蕎麦も簡単につながります。
農業振興公社が西上農園に吸収されることになりましたとの報道がありました。どんな蕎麦粉が出るのか興味があります。 |
| 江丹別産 |
価格は高い方ですが、とてもおいしい粉です。どの粉も良いのですが、特に石臼挽きは優れものです。偽装事件が発生したのは非常に残念です。農家の方々が気の毒です。 |
| 浦臼産 |
14.10~ 浦臼牡丹蕎麦まつりに参加
蕎麦まつりで販売していたのはロール挽きの3番粉です。色が真っ黒です。食べると蕎麦の香りが強く、コシもすごくありました。
普段、取り寄せているのは、「ぬき」を石臼挽きにした粉です。最近はもっぱらこの粉を打っています。食べた人の評価もすこぶる良く、水回しの際の香りの強さとその持続性は今まで打った蕎麦粉の中では一番です。もちろん、食べてもコシがあり、喉ごしも良く、味もとてもよい。鹿追産にも共通していますが、どちらも品種はボタン種です。
|
| 士別産 |
有機栽培の蕎麦粉を手に入れることが出来ました。価格も手頃です。浦臼産が切れたので最近はもっぱらこの粉を使っています。 |
| 知床産 |
余り良いとは感じませんでした。時間が経ちすぎ保存が悪く古くなったのかもしれません。 |
| 大雪産 |
これも余り良いとは感じませんでしたが、やはり、保存の仕方が悪かったと思います。 |
| 清水町「目分料」 |
帯広の教え子のお土産や,鈴木氏が出張した際に購入してきてくれるなど随分打ちました。抜きを石臼挽きしたものでとても良い粉です。美味しい。 |


 15.9~ 「世界そばフェスタ」や蕎麦まつりに参加
15.9~ 「世界そばフェスタ」や蕎麦まつりに参加 15.11~蕎麦イベントに使いたくてコープから送ってもらいました。田舎蕎麦系です。風味があり、蕎麦好きには大人気でした。送料等プラスアルファーが多いのがマイナス。
15.11~蕎麦イベントに使いたくてコープから送ってもらいました。田舎蕎麦系です。風味があり、蕎麦好きには大人気でした。送料等プラスアルファーが多いのがマイナス。